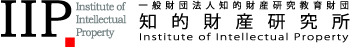知財研フォーラム

知財研フォーラム 2008 Autumn Vol.75
2008年11月発行
在庫なし
| Contents | |
|---|---|
| 巻頭言 |
|
|
|
| 【特集】著作権制度のリフォーム | |
| 2 | 著作権制度のリフォームについて |
| 茶園 成樹(ちゃえん しげき)〔大阪大学大学院高等司法研究科 教授〕 | |
| 著作権法は、社会や技術の変化に対応して頻繁に改正されているが、現在、これまでの対応とは異なり、著作権法を全面的に整理し直そうとする著作権制度のリフォームに関する議論がなされている。本稿においては、著作権制度のリフォームとして、保護対象、保護主体、著作者人格権、著作権、著作権制限、権利侵害、保護期間、著作物の利用について、改正すべき点を検討する。 | |
| 9 | フェアユースの立法論 |
| 椙山 敬士(すぎやま けいじ)〔虎ノ門南法律事務所弁護士〕 | |
| わが国でも、著作権の一般的制限規定(フェアユース)を創設すべきであるという意見が高まってきている。本稿では、第1で、フェアユースに関し、立法の必要性、経済的要素の重み付け、予測可能性の問題について一覧した後、第2で、一般的規定を導き出す前提として、個別的規定の比較、政策的根拠の整理、「フェアユース」の観点からの我が国の従来の判例の検討を行ない、第3で、立法の形式についての一案を提示した。 | |
| 15 | 著作権法上の権利処理にかかわる問題 -デジタル・コンテンツの流通促進に関する議論との関係- |
| 蘆立 順美(あしだて まさみ) 〔東北大学大学院法学研究科 准教授〕 | |
| デジタル・コンテンツの流通を促進するためのポイントは、著作権法上の権利処理の煩雑さとそれにかかる費用の問題の解消にあるとする見解は多い。本稿は、著作権法における権利処理に関する制度と権利処理の現状について概観し、現在議論の対象となっているコンテンツ流通促進法の意義と著作権法との関係について整理をするものである。 | |
| 22 | 著作権保護期間の延長問題 -著作権という壮大な社会実験におとずれる転機- |
| 福井 健策(ふくい けんさく) 〔骨董通り法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士〕 | |
| アメリカの外交要求に端を発し、延長は既定路線と目されてから2年。草の根から慎重論が巻き起こり、オープンな審議会での討議を経て「延長見送り」が報道されるまでに至った著作権保護期間の延長問題。「延長の社会的メリット」と「現行期間の社会的メリット」を実証的に比較考量し、本当のクリエイター支援策と利用促進策を考えることから、著作権の将来像が見えてくる。 | |
| 28 | 著作権の間接侵害をめぐる立法のあり方(上) |
| 島並 良(しまなみ りょう) 〔神戸大学大学院法学研究科 教授〕 | |
| 著作物の無断利用(直接行為)を助長する行為(間接行為)を、差止請求の対象とすべきか。このいわゆる著作権の間接侵害論には、著作物の利用主体性を拡張する構成と、著作権の侵害主体性を拡張する構成の2つがあり、またそれぞれの構成について解釈論と立法論が展開されている。本稿は、それらの当否を順に検討した上で、望ましい立法のあり方を探る。 | |
| 【寄稿】 | |
| 32 | 新しいタイプの商標と商標法の新しい理論 |
| 小塚 荘一郎(こづか そういちろう) 〔上智大学 教授〕 | |
| 音や色、動きなど、伝統的な文字や図形とは異なる「新しいタイプの商標」が、各国で登録を認められつつあり、WIPOのような国際的な場でも議論の対象となっている。一見すると特殊な問題のように見えるが、そこでは、商標の識別性とは何か、出願手続は誰のどのような利益を守るためにあるべきか、といった商標法制の基本問題が問われている。日本でも、大きな視野に立って議論を始めることが必要であろう。 | |
| 【コーヒーブレイク】 | |
| 38 | WIPO新事務局長誕生 |
| 夏目 健一郎(なつめ けんいちろう) 〔在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官〕 | |
| 【連載】 | |
| 43 | 知財裁判史-訴訟実務パイオニアの証言- 最終回 田倉 整弁護士 |
| R.ポーク・ワーグナー 〔ペンシルバニア大学 教授〕 | |
| 60 | 著作権と文学者-4 アンソニー・トロロープと著作権に関する王立委員会 |
| 園田 暁子(そのだ あきこ) 〔中京大学 国際教養学部 准教授〕 | |
| 64 第58回ワシントン便り | |
| 中槇 利明(なかまき としあき) 〔(財)知的財産研究所 ワシントン事務所 所長〕 | |
| 知財研NEWS | |